安全靴は、作業中の足を守るための必須アイテムですが、雨や水場での使用となると「防水性」が大きなポイントになります。
一言で防水といっても、完全防水構造のものから表面に水を弾く加工だけを施したものまで性能はさまざまです。選び方を間違えると、すぐに内部まで水が浸入してしまい、不快感や作業効率の低下につながります。
この記事では、防水規格と撥水の違いをわかりやすく解説し、雨天・水場で快適に作業するためのコツ、そして使いやすい防水スニーカータイプのおすすめポイントまで詳しく紹介します。
防水規格と「撥水」の違いを理解する
安全靴の選び方で迷うポイントのひとつが、「防水」と「撥水」という表記の違いです。一見似たように見えますが、性能や使えるシーンは大きく異なります。まず「防水」とは、靴の内部に水が浸入しないように構造そのものが設計されていることを意味します。具体的には、縫い目部分を特殊なテープで塞ぐシーリング加工や、防水性のあるメンブレン(フィルム)をアッパーに内蔵することで、外部からの水の侵入を防ぎます。防水性は「JIS規格」や「IPX規格」などで性能が試験され、一定時間・一定水圧に耐えられることが確認されています。たとえばIPX5やIPX7といった表示は、防水性能のレベルを数値で表したものです。
一方、「撥水」は素材表面に水を弾く加工を施しているだけで、水そのものを完全に防ぐ構造ではありません。雨粒や水滴をはじくことはできますが、長時間の雨や水たまりの中を歩くと徐々に水が染み込みます。撥水加工は軽量で柔軟性がある反面、過酷な水場作業や豪雨には向かず、短時間の小雨や水はね程度での使用が適しています。
つまり、防水安全靴は「中まで水を通さない」、撥水安全靴は「短時間なら水をはじく」という明確な違いがあります。現場の環境や作業内容に応じて、どちらが必要かを見極めることが重要です。特に水回りや屋外作業が多い方は、防水規格の有無を確認して選ぶことで、快適性と耐久性の両立が可能になります。
雨天・水場での快適性を上げるコツ
防水安全靴は確かに水から足を守ってくれますが、実際に長時間履くと「蒸れる」「重い」「硬い」といった不快感を感じることがあります。そこで、雨天や水場での作業をより快適にするための工夫を紹介します。
まず一番のポイントは湿気対策です。完全防水構造は外からの水を防ぐ反面、内側の湿気が逃げにくくなります。そのため、吸湿速乾性の高い靴下を選んだり、通気孔付きインソールを使用すると、足の蒸れを軽減できます。また、作業後は靴の中をしっかり乾燥させることも重要です。乾燥剤やシューズドライヤーを使えば、翌日も快適に履けます。
次にフィット感の調整です。防水靴は素材が硬めで、履き始めは足になじむまで時間がかかります。靴ひもの結び方を工夫して足首や甲の圧迫を減らす、またはクッション性の高いインソールに交換して衝撃を和らげることで、疲労を大幅に軽減できます。
さらに、雨天時は滑り止め性能が安全性に直結します。水や油がある床でも滑りにくい耐滑ソールを備えたモデルを選ぶことで、転倒リスクを減らせます。特に厨房や食品工場、港湾作業などでは、防滑性の高いソールが必須です。
防水性能だけでなく、蒸れ対策・フィット感・防滑性を総合的に考えることで、雨や水場でも快適に作業を続けられます。
防水スニーカータイプおすすめ
近年は、作業現場でも履けるカジュアルな見た目の防水スニーカータイプ安全靴が増えています。見た目はスニーカーでも、つま先には鋼製や樹脂製の先芯が入り、耐久性や安全性も確保されているのが特徴です。
おすすめのタイプとしてまず挙げられるのがBoaダイヤル式防水スニーカーです。ダイヤルを回すだけでフィット感を調整でき、脱ぎ履きが素早く行えます。雨の日や頻繁に靴を脱ぐ現場作業では、この機能が大きな時短効果を発揮します。
次に防滑ソール付きミドルカットモデル。足首まで覆うことで水の侵入を防ぎつつ、軽量設計で動きやすいのが魅力です。港湾や建設現場など、足首の保護が求められる現場にも向いています。
さらに軽量EVAミッドソールタイプも人気です。防水構造でありながら、クッション性と軽量性を両立しており、長時間の立ち作業や歩行でも疲れにくくなっています。
このように、防水スニーカータイプは安全性だけでなく、快適性やデザイン性も重視できる点が大きなメリットです。現場での作業後、そのまま街中を歩いても違和感のないデザインが多く、通勤や普段履きにも兼用できます。雨の日でも快適でスタイリッシュに過ごしたい方には、まさに理想的な選択肢といえるでしょう。

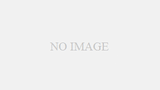
コメント