製造業や電子部品の取り扱い現場では、作業者の安全と製品の品質を守るために、帯電防止機能を備えた安全靴が欠かせません。この記事では、ESD(静電気放電)の基礎から、帯電防止靴の選び方や注意点、さらに静電対策モデルの比較と運用ポイントまでを詳しく解説します。
ESDの基礎と現場リスクの整理
ESD(Electrostatic Discharge)とは、物体に蓄積された静電気が瞬間的に放電される現象を指します。人間は日常的に数百Vから数千Vの静電気を帯びることがあり、電子部品や精密機器の製造現場ではこの放電が重大な不良や破損の原因となります。特に半導体や基板などは数十V程度の電圧でも損傷を受けるため、作業者からの静電気放電を抑えることが重要です。現場では、気温や湿度の低下、化繊衣類の着用、床材の特性などが帯電リスクを高めます。また、静電気は目に見えず音も伴わないため、気づかないうちに製品や設備にダメージを与えてしまう可能性があります。そのため、床面・衣類・手袋・そして足元までを含めた総合的なESD対策が必要不可欠です。
帯電防止靴の選び方とNG例
帯電防止靴は、靴底から地面へと帯電を安全に逃がす構造になっており、ESDリスクを軽減します。選び方のポイントとしては、まず帯電防止性能(抵抗値)が国際規格(ISO 20345やJIS規格)を満たしているか確認することです。一般的には、100kΩ以上1GΩ未満の抵抗値が求められます。また、作業環境に合わせて耐油性、滑り止め性能、つま先保護(スチール・樹脂)などの機能も考慮します。一方で、NG例としては以下が挙げられます。①普通のスニーカーや安全靴を「なんとなく大丈夫」と使う、②靴底が摩耗して導電性能が低下している、③インソールを市販の絶縁タイプに交換してしまう、④湿度管理が不十分な環境で使用し続けるなどです。帯電防止靴は導電性能が劣化するため、定期的な測定や交換が不可欠です。
静電対策モデル比較&運用ポイント
帯電防止靴には、さまざまなモデルがあります。例えば、軽量で通気性の高いメッシュタイプは夏場の作業に適し、耐久性重視のレザーモデルは重機や屋外作業向きです。また、メーカーによってはESD対応マークや抵抗値測定結果を明記している製品もあり、信頼性の指標となります。比較の際は、重量、履き心地、通気性、耐久性、価格のバランスを考慮します。運用面では、靴底の清掃を習慣化すること、湿度管理を行うこと、インソール交換時に必ず導電性能を確認することが重要です。さらに、月1回程度の抵抗値測定を行い、規格外となった場合は即交換するルールを設けることで、ESDリスクを大幅に低減できます。単に「履くだけ」ではなく、日々のメンテナンスと管理体制が現場の安全を左右します。
まとめ
ESD対策において帯電防止靴は欠かせない要素であり、その性能や状態が現場の品質と安全に直結します。選定時には規格適合や作業環境への適合性を確認し、使用中も摩耗や性能劣化に注意を払うことが必要です。また、モデル比較や運用ルールの整備により、ESDリスクを最小限に抑えることができます。足元からの静電気対策を徹底し、安心・安全な作業環境を実現しましょう。

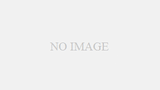
コメント